代表よりひとこと
さる6月1日に県民公園太閤山ランドで行われた「いっちゃん!リレーマラソン2025」のフルマラソン部門にチーム「ほくりくでんせつのひと」として、社員から18名の精鋭を集め参加して来ました。競技方法はリレーマラソン方式で1周約2.1kmのコースを20周約42㎞をタスキリレーして完走する競技です。走る順番や何周走るかは各チームの自由となっています。結果はケガ人も出すことなく3時間33分で無事完走を果たしました。私は走りたい欲求をこらえ応援団に徹していました。以前に環水公園で行われていたあいの風リレーマラソンに4回ほど参加していました。今回は8年振りのリレーマラソンに、時が変わりメンバーが変わって参加しましたが社員が一丸となり声を掛け合い一本のタスキをつなぐリレーマラソンは変わらず毎回熱気を感じました。日頃見れない社員の一面も見られ、社員の絆がより一層強固なものになったと実感できる良きイベント参加でした。次回も機会があれば奮って参加し、その時はランナーとしても…。
代表取締役社長 藤岡健一
スタッフコラム
菌活の日
Tさん
「うわっ、もう順番が回ってきた!」ロッカーに配られた原稿用紙を見て自由テーマに悩む時間がきました。いつもながらあれこれと考えてはみるものの何も思い付かず、サラッと書ける人が本当に羨ましいです。
さて、少し字数を稼いだところで「今日は何の日」を調べてみると5月24日はゴルフ場記念日、ブルボン・プチの日など色々ある中に菌活の日という自分にとって興味深いものがありました。温活,眠活,脳活,筋活など色々ありますが、菌活とは身体に影響の良い善玉菌を増やす効果のあるものを積極的に取り入れ腸内環境のバランスを整える生活習慣のようで、腸活イコール菌活とも思える大事なことのようです。そんな大事な菌活の日は某株式会社が「菌活」という言葉をテレビCMで初めて全国発信した5月24日を記念日として制定し、今年で10年目を迎えたそうです。
菌活を始めるには
1.きのこを毎日1回食べるように心掛ける。
2.ヨーグルトや納豆などの発酵食品を毎日食べる。
3.野菜や果物を沢山食べる。
4.毎日同じ時間に規則正しい食生活を心掛ける。
5.毎日30分以上のウォーキングを心掛ける。
6.毎日8時間以上の睡眠を取りましょう。
とあり、言葉では簡単ですが「腸内フローラ」と呼ばれる善玉菌・悪玉菌・日和見菌を2:1:7になるように食事を取るのはもちろん、運動・睡眠もなかなか規則正しく出来ず難しいのが現実です。ですが第2の脳と呼ばれる腸を整える菌活には腸内環境改善・免疫力向上・健康維持など色々な良い効果が期待できることを考えると菌類の摂取・健康的な生活を送ることを目指す「菌活の縁」を大事にして初めは緩くからでも始めようと思いました。
振り返り
Yさん
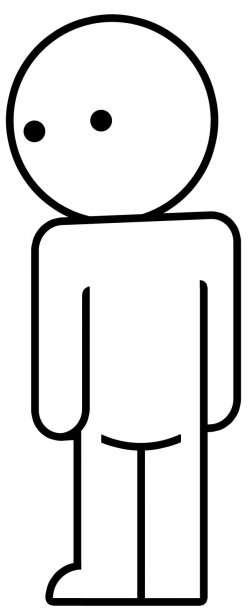 こうして北設ニュースの原稿を書くのも3回目になりますが、1回目はコロナ渦だったのでそのことを、2回目は少し前に始めていた積み立て投資について書きました。当時の原稿を見返すと、その当時あったことを振り返る良いツールになっていると感じました。そんな訳で今回は、前回に原稿に書いてから現在までの2年間についてを中心に書いていこうと思います。
こうして北設ニュースの原稿を書くのも3回目になりますが、1回目はコロナ渦だったのでそのことを、2回目は少し前に始めていた積み立て投資について書きました。当時の原稿を見返すと、その当時あったことを振り返る良いツールになっていると感じました。そんな訳で今回は、前回に原稿に書いてから現在までの2年間についてを中心に書いていこうと思います。
去年、北陸電設は日本海ガス絆ホールディングスのグループ会社となりました。それに伴い給与体系や作業服も変更になりました。作業服が変わった際には大分違和感がありましたが、両親や立山マシンの人からはおおむね好評でした。仕事としてはこの2年間は東洋電制や立山マシン、どちらもない時は会社勤務と行ったり来たりしていました。特に立山マシンでは1年間で工場内での異動が4回あってそのたびに仕事内容がガラッと変わるので、その都度一から覚えて慣れるまでが特に大変でした。しばらくは今居る婦中工場での勤務が続くようなので、ある程度、落ち着いて仕事が出来そうです。
朝、テレビを見ていると、毎日のように物の値上がりのニュースが流れます。最近は米の値上がりが特に注目されていますがそれ以外でも様々なものが値上がりしています。米の値上がりには備蓄米を、ガソリンには補助金をそれぞれ出すようですが、いずれも対症療法でしかなく、原因が取り除かれていないため効果は限定的になりそうです。
月々の出費が上がる中で、とりあえず手っ取り早く給料を上げようと思い、昨年建設業経理士の資格を取得しました。月々4,000円、年間だと48,000円が資格を持っているだけで入ってくるのは正直かなり助かります。今年はもうすぐ施工管理の試験が控えているので給料UPのために頑張ります。
動機が不純な気がするのはきっと気のせいです。
交通ルールについて
Tさん
 交通ルール・マナーについて皆さんどのように考えていますでしょうか。もちろんマナーとルールは規則等の有無で違いますが、ルールのみに焦点を置いてみましょう。
交通ルール・マナーについて皆さんどのように考えていますでしょうか。もちろんマナーとルールは規則等の有無で違いますが、ルールのみに焦点を置いてみましょう。
例えば、横断歩道待ちしている歩行者が先どうぞとジェスチャーしていても捕まる場合があります。この例は特別で後々覆ったりする場合もありますが、基本的は譲られても譲り返す精神でいることが安全だと思います。他にも教習所で学ぶことですが、後ろの車に追い越しされる場合に譲らず、スピードを上げてしまうと走行妨害にあたり交通違反になります。抜かされても焦らず怒らずいつも通りの運転を心がけましょう、もし腹が立ってスピードを上げてくっ付いてしまうと、煽り運転として検挙されてしまう場合があるので注意が必要です。
地域にもよりますが、小学・中学校の付近ではよくスクールゾーンの標識があることが多いです。場所によっては時間帯が朝の6時半からの所がちらほらとあります。大体のスクールゾーンでは基本的に7時から9時半が多いので近場に学校がある方は注意が必要です。検挙数が一番多いのが一時不停止です。最近私も運転していると不停止の取り締まりしているのをかなり見かけます。一人一人の意識が変わらない限り違反はなくならないだろうなと感じます。
近年富山県の道路交通法違反検挙件数が高まっております、2022年には全国1位(悪い意味で)になり違反者数が多く、検挙の取締りが厳しいということが読み取れます。富山県内でも全国ニュースになるほどの大きな事件がいくつか起きているので、かなり厳しい目で見張っているのではないかと思っています。これを調べていると自分も他人事ではないと感じ、今後も運転する時には安全運転を心がけていこうと思います。
今月のトピックス
業務(受注・竣工等)
- 市営八尾コミュニティバスEVバス車内デジタルサイネージ設置業務委託を竣工
- 富山県立中央病院6階南病棟照明設備等修繕工事を竣工
その他

- 建設業許可を更新しました。
- R7年4月14日(月)7:30~当社屋にて健康診断を行いました。
- 5月26日畠山さんが顧問を退任されました。お疲れさまでした。
現場リポート ~社員の経験値~
4月中旬から某所にて工場新築工事がスタートしました。今回は設計から携わりお客様の要望を取込み、施工についても工場内の電気設備(強電・弱電)を一括に受注しています。工程として建屋完成後に設備機器が導入される流れで、工場内の電気工事以外に設備機器に対する電気工事も請け負っており、完成は9月下旬の予定です。現在は建屋内部の作業中です。
現場代理人は今回初めて建物の新築物件を担当し、お客様との調整、施工図の作成に努力しています。職長は勤続5年目になった社員が初めて職長として現場に携わっています。初めての職長で不安なことも多くあるようですが周囲に相談し、助け合いながら作業を進めています。社員は日々経験を積みながら成長しています。


学び舎 ~施工管理検定にむけて~
 これ、いい問題ですよね。個人的には電気系の資格試験において絶対的に理解している方がいいと思っています。インピーダンス、電流、有効電力、無効電力、そして皮相電力その辺が理解出来ると思っています。インピーダンスを求める際はピタゴラスの定理、古代ギリシャの数学者ピタゴラスの名前が、其れを日本語で表すと三平方の定理、こんなにも詰まっています。
これ、いい問題ですよね。個人的には電気系の資格試験において絶対的に理解している方がいいと思っています。インピーダンス、電流、有効電力、無効電力、そして皮相電力その辺が理解出来ると思っています。インピーダンスを求める際はピタゴラスの定理、古代ギリシャの数学者ピタゴラスの名前が、其れを日本語で表すと三平方の定理、こんなにも詰まっています。
4月から勉強会で電気施工管理一次試験突破にむけて受験者が真剣に勉強をしています。その為に私が出来ることは比較的に出る問題をピックアップして一緒に解くぐらいです。例えばTV系、光系に関しては、考える事ではなく覚える事ですよ、と言うだけ。受験者が真剣に向き合えば確実に突破できます。
地域活動 ~リレーマラソン~

令和7年6月1日(日)に日本海ガス絆ホールディングス特別協賛である「いっちゃん!リレーマラソン2025」に参加しました。グループになってから初参加になります。社員での参加は「富山あいの風マラソン」以来の8年ぶりで、マラソン自体は今回で5回目となります。今年は社員の家族や50代の社員も参加しました。記録を遡ったところ、総合記録は徐々に速くなっています。
当日は約700チーム6500人を越えるランナーと応援者も入れておよそ25000人が来場し、会場が盛り上がりました。一時雨が降る天気でしたが皆で怪我もなく無事に完走することが出来ました。ランナーや応援者も笑顔にあふれ、絆グループでの参加を通して地域活性化に協力できたと感じています。
熱中症の発生が相次ぐ中、職場においても例年、熱中症が多数発生しており、ここ数年、重篤化して死亡に至る事例が年間30人程度発生する状態が続いていることから、本キャンペーンを通じ、すべての職場において、基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかける。
厚生労働省 実施要項より抜粋

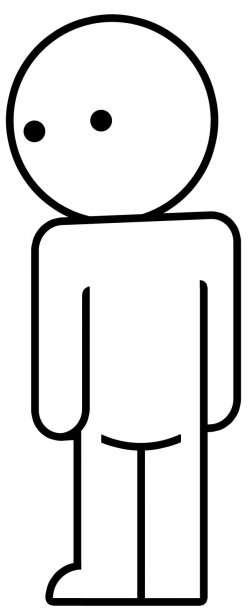 こうして北設ニュースの原稿を書くのも3回目になりますが、1回目はコロナ渦だったのでそのことを、2回目は少し前に始めていた積み立て投資について書きました。当時の原稿を見返すと、その当時あったことを振り返る良いツールになっていると感じました。そんな訳で今回は、前回に原稿に書いてから現在までの2年間についてを中心に書いていこうと思います。
こうして北設ニュースの原稿を書くのも3回目になりますが、1回目はコロナ渦だったのでそのことを、2回目は少し前に始めていた積み立て投資について書きました。当時の原稿を見返すと、その当時あったことを振り返る良いツールになっていると感じました。そんな訳で今回は、前回に原稿に書いてから現在までの2年間についてを中心に書いていこうと思います。 交通ルール・マナーについて皆さんどのように考えていますでしょうか。もちろんマナーとルールは規則等の有無で違いますが、ルールのみに焦点を置いてみましょう。
交通ルール・マナーについて皆さんどのように考えていますでしょうか。もちろんマナーとルールは規則等の有無で違いますが、ルールのみに焦点を置いてみましょう。


 これ、いい問題ですよね。個人的には電気系の資格試験において絶対的に理解している方がいいと思っています。インピーダンス、電流、有効電力、無効電力、そして皮相電力その辺が理解出来ると思っています。インピーダンスを求める際はピタゴラスの定理、古代ギリシャの数学者ピタゴラスの名前が、其れを日本語で表すと三平方の定理、こんなにも詰まっています。
これ、いい問題ですよね。個人的には電気系の資格試験において絶対的に理解している方がいいと思っています。インピーダンス、電流、有効電力、無効電力、そして皮相電力その辺が理解出来ると思っています。インピーダンスを求める際はピタゴラスの定理、古代ギリシャの数学者ピタゴラスの名前が、其れを日本語で表すと三平方の定理、こんなにも詰まっています。